

 |
 |
||
|
|
|||
|
|
福井県の新羅神社(5) 若狭地方の新羅神社 (ニ)新羅神社の由来 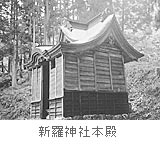 神社がある今庄町について『福井県南条郡誌』は次のように説明している。地理的には、京畿東山東海三道の諸地と北陸諸国とを連絡する咽喉の要地を占め、北陸の関門たる枢要の地域を成し交通上軍事上極めて重要の所なり。往古は叔羅駅の所在地とも称され、中古庄園の一つとして今庄と称されたものであろうか。また今庄は今城と書かれたという。 神社がある今庄町について『福井県南条郡誌』は次のように説明している。地理的には、京畿東山東海三道の諸地と北陸諸国とを連絡する咽喉の要地を占め、北陸の関門たる枢要の地域を成し交通上軍事上極めて重要の所なり。往古は叔羅駅の所在地とも称され、中古庄園の一つとして今庄と称されたものであろうか。また今庄は今城と書かれたという。更に『福井県南条郡誌』は、白城神社について次のように記載している。白城神社は『古名考』によれば「或云白木浦の社乎、案南条郡今庄町に新羅(しらぎ)明神あり是なるべし。今庄も古く今城と書けり。此白城の誤転する乎。此町の東に川あり日野川と云此即古の叔羅河なり。叔羅は即ちしらきなるべし」
これによれば、今庄町は新羅(しらき)から白城→今城→今庄と変わってきたことになる。白城はしらぎと呼ばれたであろうし、今城はいまきからいまじょうに変わったということになる。今城(いまき)は今来の漢人を連想させる(五世紀後半の雄略天皇の時代)。
結論として、今庄町について『南条郡誌』は「要するに今庄の地は、新羅民族の移住地として開け、次いで駅伝所在の要地となった」とまとめている。
また『南条郡誌』は、信露貴彦神社の項では次のように記載している。信露貴彦神社或は堺村荒井の新羅(しらぎ)神社ならん乎。
『古名考』一説日野川の源夜叉ケ池に古へ新露貴神社あり故に此河の渡所を白鬼女村と云は信露貴彦の訛なりと云へ共然らじ。
夜叉ケ池は古くは尸羅(しら)池といわれていた。
『福井県今庄の歴史探訪』の説明によれば、今庄宿(じゅく)の神々について「三韓・新羅はわが国の弥生・古墳時代に当っており、この頃今庄へも新羅の渡来民があり、この地を開発したであろうことが推測される。新羅(シラキ)の宛字と思われる神社名や土地名が敦賀付近には多い。
例えば敦賀市の白木、神社名では信露貴彦(しろきひこ)神社・白城(しろき)神社・白鬚(しらひげ)神社などである。今庄宿の新羅(しんら)神社は古くからの産土神で、江戸時代には……〈上の宮〉と称され、白鬚神社は〈下の宮〉と称された」。
いずれにせよ、古代朝鮮の新羅の民が敦賀地方から今庄に入り、日野川上流域を開発したものであろう。新羅神社や白鬚神社は渡来人の奉祀に始まる神々と関係が深いようである。中でも、当地方には秦氏が集住していたと考えられている。足羽郡や三方郡・遠敷郡に多くの秦氏の集団跡が確認されている。
荒井地区の新羅神社は現在でもしらぎ―神社と称されている。足立尚計は『日本の神々』の中で今庄宿の新羅神社をしらぎ神社であると紹介し、園城寺の「新羅善神堂」もしらぎ善神堂と紹介している。
更に『越前国古名考』は今庄の新羅神社を式内社の白城神社であるとしている。朴春日「古代朝鮮と日本の旅」では、「火燧山の嶺山(元は新羅山と呼ばれていたであろう)に新羅神社が鎮座していたが、源義仲が城を築くため臨時に小社を建てて祭神を移した。その後社殿を再建したが、小社の方は白城神社として残り、本社の方は新羅神社の名をそのまま引きついだ」と説明している。
『越前国名磧考』によれば、「当社は、往古燧山の山頂に鎮座していたが、寿永二年(一一八三)に源義仲が是に城郭を築こうとして、傍に小社を建てて遷座した。其の後、越前国を鎮定して社殿を再建し深く崇敬した」と記し、更に「天文年中(一五三二〜一五五五)に郷民が協議して当今の社地に神殿を新築して、茲に神璽を遷座して以来、今に至るまで氏神として敬い奉斎している」と記している。
今庄町今庄の白鬚神社の祭神が猿田彦命・大己貴命・少彦名命であることは、当社も新羅系であったことを推測させる。
(三)白鬚(白城)神社 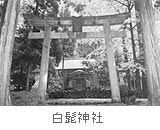 武内宿禰と係りの深い白鬚神社が今庄町合波にある。祭神は武内宿禰尊・天御中主神・宇賀御霊神・鵜葺草葺不合尊(うがやぶきあえず)・熊野大神・豊受大神・大己貴命・猿田彦命・春日大神・秋葉大神・金山彦命・土不合命・八幡大神・清寧天皇・吉若大子。『福井県神社誌』等で当社の由緒を調べてみると、「当社の創立の年月不祥。往昔は白城神社と称し、式内社であったという。口伝によれば、神功皇后が三韓征伐から凱旋の後、皇子(後の応神天皇)を降誕したが、皇子に飲ませる乳が足りなかったので、武内宿禰大臣が神々に祈願したところ、“越の国南端の三尾の郷(日野川の上流にある八飯・宇津尾・橋立・広野の村々)に西向の滝(高さ十二m、幅二m。信露(しろ)滝)がある。その水を乳婦に勧めよ”とのお告げがあり、武内宿禰が尋ね歩いたところ、神託通り西向の滝があり、乳婦に飲ませると神託の通りの功験があった」とある。 武内宿禰と係りの深い白鬚神社が今庄町合波にある。祭神は武内宿禰尊・天御中主神・宇賀御霊神・鵜葺草葺不合尊(うがやぶきあえず)・熊野大神・豊受大神・大己貴命・猿田彦命・春日大神・秋葉大神・金山彦命・土不合命・八幡大神・清寧天皇・吉若大子。『福井県神社誌』等で当社の由緒を調べてみると、「当社の創立の年月不祥。往昔は白城神社と称し、式内社であったという。口伝によれば、神功皇后が三韓征伐から凱旋の後、皇子(後の応神天皇)を降誕したが、皇子に飲ませる乳が足りなかったので、武内宿禰大臣が神々に祈願したところ、“越の国南端の三尾の郷(日野川の上流にある八飯・宇津尾・橋立・広野の村々)に西向の滝(高さ十二m、幅二m。信露(しろ)滝)がある。その水を乳婦に勧めよ”とのお告げがあり、武内宿禰が尋ね歩いたところ、神託通り西向の滝があり、乳婦に飲ませると神託の通りの功験があった」とある。武内宿禰という人物は、朝鮮渡来系の豪族の共同の「父」として、朝鮮南部と倭国の大和との接点として設定されている。応神天皇が武内宿禰と共に敦賀の笥飯(けひの)大神を拝んだことなどの説話からすれば、当地方も越前の一地方として大きな一つの文化圏の中にあったと考えられる。これらの渡来系の人々は弁辰の地の倭種であろう(『清張通史』)。
当地方には、高麗系や新羅系の渡来人が混在していたのかも知れない。当地方の神社は信露貴彦・白城・新羅など、社の由緒や呼び名が同一であったことは、古代においてはこれらの地域が同一の生活圏であったことを示すものと考えられる。
(四)藤倉山と修験道 新羅神社が鎮座していたといわれる燧ケ城のあった愛宕山の城について『源平盛衰記』は、「海上遠く打廻り越路遥かに見え渡る。磐石高く聳え挙がって四方の峰を連ねたれば、北陸第一の城郭なり」と記している。背後の藤倉山(六四三m)の頂上からは敦賀半島や日本海が一望できる。
藤倉山は今庄宿の惣社として藤倉権現が祀られていたという。「古昔は藤倉山の鍋蔵院東照寺と云天台宗の大坊有」(『今庄宿惣社祭神末考』)。
藤倉山は古くは修験の行場であったといわれている。山麓に石組の石室や社檀・寺址・行場跡らしい遺跡が残っており、藤倉山の懸崖や多くの巨岩について『藤倉山遺跡考』(藤本浩一)では「これはどうみても古代の磐座としか考えられない」という。修験道を通じて園城寺との係りがあったのかも知れない。
今回の訪問では、前宮司の加藤久子氏にお目にかかり
いろいろとお話が聞けた。拝殿・二社殿・五社殿(新羅宮(しらぎのみや))を拝観できたが、五社殿には不動尊が多く置かれていた。愛宕山から出土したという不動尊も安置されていた。帰る際には、新羅宮で配る結婚式の若狭塗の夫婦箸をいただいた。
出羽弘明(東京リース株式会社・常務取締役)
<< 福井県の新羅神社(4) | 京都府の新羅神社(1) >>
・「新羅神社考」に戻る ・「連載」に戻る |