

 |  | ||
|
|
|||
|
|
東北地方における新羅神社(2) (4)神社と源氏三兄弟のつながり
これらの神社と源氏三兄弟が結びついていることも大変興味深いが、
この伝承は源氏三兄弟の時代より後代に創られたものであろう。
或いは渡来系の秦氏と係りのあった人々が、この地に居を構えて京都・近江地方と同様な形で源氏三兄弟
と共に神を祭ったとも考えられる。
新羅三郎義光は甲斐の国守であったが、当地には甲斐の国とのつながりを示す伝承がある。
伝承の真意は明確ではないが、当地方と新羅三郎義光やその子孫の住した山梨県との係りを示しているようである。高畠町にある「犬の宮」と「猫
の宮」にまつわる伝承がそれである。
山崎正『修験と犬の宮伝説考』によれば、
「高安の山奥、舞台岩に住みついた古狸が役人に化け、毎年人年貢を取り、人々を悲しませていた。 それをみかねた愛宕山(源福寺の裏)の地蔵権現が… 甲斐国から三毛犬四毛犬(めっけげすっけげ)を連れてきて古狸を退治した。 この際に死んだ犬を葬ったのが犬の宮である…」 「犬宮伝説の年代は出羽国が建置(七一二年)された八世紀 の始め頃と考えられ…」「高安地区にある犬の宮別当正真山 林照院は天台宗に属し修験者林照坊を祖としている。縁起に よると ”山中に住む狸が人々を困らせていたが、聖真子に追い払われ甲斐国八代郡に逃げ込んだところ、 またまた南宮宝性大菩薩の宮犬三毛犬四毛犬に追いたてられ” …現在山梨県八代郡には犬の宮伝説を裏づける”南宮宝性大神社”は見当らないが、 『甲斐国志巻之五十五』によれば、 「南宮明神即ち諏訪明神なり武田家世々尊崇する所なり云々」とあるところから、 「或いは信濃・甲斐一帯の勧請末社の一つとみてもよい」と説明されている。
これらの伝説が甲斐の新羅三郎義光との関係を示すものと考えれば、
神社は源氏三兄弟が活躍した1050年頃より後代のものと考えられ、新羅神社は山梨県の南部町、
ひいては近江の三井寺の新羅神社から勧請されたことになる。
(5)高畠町の白髭神社について 
社名は新羅神社ではないが、近江からの勧請といわれる白髭神社が新羅神社の近くにある。
新羅神社から車で五〜六分、国道113号線を西に進み歩道橋を過ぎたところの右手に竹森山があり、
その麓が白髭神社の森である。神社は山裾の急な石段の上にある。百段位はありそうである。
縄文時代からの遺跡である日向洞窟への標識板が石段の横に掲げられてある。
南向きに石の鳥居があり、その右手に石灯篭と石碑が立っている。
『山形県の板碑文化』によれば「此の白髭神社は元白髭明神で、元文元年七月出版の米沢事跡考によれば、
猿田彦命を祭り伊達家の家臣・近江国滋賀郡出身小松某の祖が勧請した旨記されているが、
元来同神は大陸から帰化して近江を開墾した氏族の祭神であったものを本地垂迹説から猿田彦に転じ
たものである。近江国の同神は江若鉄道白鬚駅前にある古社である」と説明している。
また『東置賜郡史』には、祭神は武内宿祢であると記載されている。
白髭神社は高畠町には三社あり、『東置賜郡史』によれば、中川村中山の郷社・白髭神社も
「和同七年(七一四)近江国白髭神社の神霊を勧請し社殿を建立したものなりといふ」としている。
白髭神社が近江からの勧請であるということからすれば、
近江出身の人々がこの地に多く移住していたことが考えられ、
前項の新羅神社も或いは近江出身の人々と係りがあるのかも知れない。
二、福島県相馬地方の新羅神社
福島県には「新羅神社」は見当らないが、平成七年九月十八日のテレビ朝日で放映された
「相馬野馬追」を見ていたところ、「神旗争奪戦」で数百騎の騎馬武者が掲げている神旗の中に
黄地に黒字で「新羅大明神」なる神旗を見たので、相馬市教育委員会に問い合わせたところ、
文化課の佐藤氏から懇切なる説明をいただいた。
即ち、「黄色地に新羅大明神と書かれた旗紋は確認できないが、
『宇多郷在郷給人旗帳』等の旗帳には白地に黒字のものはあり、一条氏の旗である。
一条氏については『衆臣系譜』によれば、「鎮守が素戔鳴尊垂迹新羅大明神、三井寺鎮守」とあり、
更に家紋は割菱(武田氏の紋)、幕紋は菅である。旗紋は「黒地に白釘抜」
「白地に黒字で新羅大明神」菩提寺は「西林山真光寺」とあり、もし黄色地の旗が一条氏関連のものであれば、
このような調査結果であります」とのことであった。
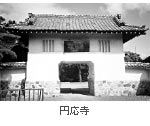
そこで「西林山真光寺」についても尋ねたところ、「西林山真光寺は円応寺の末寺であり、
天保十一年か十三年のどちらかに立谷龍朔寺に合院され、川原町の真光寺域伽藍は円応寺となったようである。
そして現在の円応寺は相馬市中村字川原町一八四番地にある」とのことであった。
なお『相馬市史』によれば円応寺については豊池山円応寺と称し、「旧小高郷小谷邑にあり、
のち中村河原町真光寺に移る。羽州米沢瑞龍院の末寺。禅三個寺の其一。
護寺神は白山権現、鶏足明神。勧請開山端龍院三世月窓正印大和尚。
豊池山鴛鴦(えんおう)寺と号したが、しばしば火災に遭い、名を円応寺と改めた」という。
更に「西林山真光寺」については、円応寺の末寺、古来中村河原町にあり。
近属龍朔寺に移り、寺宇は円応寺と為る。開山円応四世一翁全益和尚。原寺は西山岩門の西にあり。
天授院(相馬盛胤公)殿追薦冥福のために寺を天授公の墓側に移す。天保十一年円応寺を当寺に移す。…」とある。
相馬氏は元々下総国の千葉氏一族であり、文治五年(1189)の「奥州合戦」に従った功績により
千葉介常胤が浜通りの諸郡を与えられたことに始まるといわれる。
宇多郷の「新羅大明神」は「旗紋」からすれば「武田菱」であるので新羅三郎義光の系譜と繋がることになり
「三井寺鎮守」の記述もあるので、近江の三井寺とのつながりがあったことは間違いないと思われる。
しかし、いつどのように祭られたかは詳らかでない。
現在の円応寺の住職志賀氏に史料等を尋ねてみたが火災で消失し残っていないとのことであった。
古くはひな鳥寺と称したが何度も火災に遭い、ひなどりが火を呼ぶ鳥ということで円応寺に改めたと話してくれた。
出羽弘明(東京リース株式会社・常務取締役)
<< 東北地方における新羅神社(1) | 東北地方における新羅神社(3) >>
・「新羅神社考」に戻る ・「連載」に戻る |