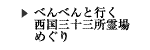その(4) 毛利輝元
新緑の三井寺境内に
 世は歴史ブームである。歴史書、観光ガイドブックを携えて三井寺を訪れる人は多い。特に戦国武将の追っかけを自認する「歴女」という言葉が定着するほどである。 世は歴史ブームである。歴史書、観光ガイドブックを携えて三井寺を訪れる人は多い。特に戦国武将の追っかけを自認する「歴女」という言葉が定着するほどである。
 天下統一という大義に、自らの才覚と人脈で覇権を争った信長や秀吉は、その興味の最たる人物と言えよう。NHK大河ドラマ『軍師黒田官兵衛』は、主君秀吉の天下取りに身を挺して、策を弄する黒田官兵衛を軸に描かれている。人はその立場で、登場人物に己の人生を投影してドラマに観入る。そんな思いで、新緑のなか三井寺を散策してみることにする。 天下統一という大義に、自らの才覚と人脈で覇権を争った信長や秀吉は、その興味の最たる人物と言えよう。NHK大河ドラマ『軍師黒田官兵衛』は、主君秀吉の天下取りに身を挺して、策を弄する黒田官兵衛を軸に描かれている。人はその立場で、登場人物に己の人生を投影してドラマに観入る。そんな思いで、新緑のなか三井寺を散策してみることにする。
三井寺境内の中心部、金堂の西側から細い道を山側に歩くと、むかで退治の伝説で有名な弁慶の引き摺り鐘が納まる霊鐘堂(重文)に行きあたる。その南隣りに室町初期の様式が色濃く残る一切経蔵(重文)がある。その一切経蔵を寄進したのが、中国・北九州の覇者、知行百二十二万石の大名まで上りつめた毛利輝元である。

 桁行三間梁間四間、重層檜皮葺きの重厚なこの一切経蔵は、三井寺境内にはめずらしい禅宗様式のお堂である。その中には中心軸で回転する八角の輪蔵があり、その輪蔵の中には高麗版の一切経が収められている。これを一回転すると一切経を音読したのと同じ功徳があると言われているありがたいお堂である。 桁行三間梁間四間、重層檜皮葺きの重厚なこの一切経蔵は、三井寺境内にはめずらしい禅宗様式のお堂である。その中には中心軸で回転する八角の輪蔵があり、その輪蔵の中には高麗版の一切経が収められている。これを一回転すると一切経を音読したのと同じ功徳があると言われているありがたいお堂である。
 毛利輝元は慶長七(一六〇二)年、自領周防(山口県)の国清寺から、この一切経蔵を移築し、三井寺に寄進している。いわば、人力、もしくは牛馬に頼るしかない時代、資材の運搬作業や、解体・組立などの難事業だったことは容易に推測できる。 毛利輝元は慶長七(一六〇二)年、自領周防(山口県)の国清寺から、この一切経蔵を移築し、三井寺に寄進している。いわば、人力、もしくは牛馬に頼るしかない時代、資材の運搬作業や、解体・組立などの難事業だったことは容易に推測できる。
今回の特集『戦国武将と三井寺』は、その一切経蔵を寄進した毛利輝元と三井寺の関係について話を進めたい。
輝元と三井寺の関係は
 時は戦国時代、安芸(広島県)の一領主にすぎなかった毛利元就(今回の主人公、毛利輝元の祖父)は、小規模な国人領主から、中国地方のほぼ全域を支配下に置くまでに勢力を拡大しつつあった。その間、因幡の尼子氏や、周防や長門にも影響力を持つ大友氏との確執は根強く、こう着状態が続いていた。この抗争に調停役を担ったのが、三井寺第百三十八代長吏、道澄であった。 時は戦国時代、安芸(広島県)の一領主にすぎなかった毛利元就(今回の主人公、毛利輝元の祖父)は、小規模な国人領主から、中国地方のほぼ全域を支配下に置くまでに勢力を拡大しつつあった。その間、因幡の尼子氏や、周防や長門にも影響力を持つ大友氏との確執は根強く、こう着状態が続いていた。この抗争に調停役を担ったのが、三井寺第百三十八代長吏、道澄であった。
道澄は天文十三(一五四四)年、関白近衛稙家の三男として生まれる。近衛家といえば、始祖・藤原鎌足公以来、朝廷最高の官職を占める五摂家の一つである。道澄は、早くから天台の門に入り、聖護院門跡、三井寺長吏、熊野三山検校などの要職を歴任している。道澄はその政治的手腕はもとより、特に詩歌の才に長けていて、たびたび西国へ赴き、厳島神社での和歌の会や、能楽を元就と共に楽しむようになった。
 また毛利家には、元就の死後、道澄が吉田郡山城で発見した和歌や連歌の遺作を、京へ持ち帰り編集・書写した『元就詠草』が残っている。 また毛利家には、元就の死後、道澄が吉田郡山城で発見した和歌や連歌の遺作を、京へ持ち帰り編集・書写した『元就詠草』が残っている。
輝元の時代になると、その関係は益々深まり『輝元公御上洛日記』には、輝元上洛の時、道澄は豊臣秀吉の住居である聚楽第に案内し、秀吉と直接歓談する労を計らっている。
また、三井寺で開かれた歌会では
“見せはやと思ひし秋の色うすき長等の山の志賀の浦風”
と道澄が詠み、
“海山の名にし負ひたる秋の色 深き心の程は見えけり”
と輝元が返している。
この交遊関係が、その後三井寺復興の大きな原動力となるが、その前に毛利輝元とはどのような人物であったのか述べてみよう。

毛利輝元は天文二十二(一五五三)年、毛利隆元の嫡男として生まれる。十一歳の時に父が急死し、家督を継ぐことになるが、祖父、毛利元就が後見人として実権を握った。永禄八(一五六五)年に元服し、室町幕府十三代目将軍、足利義輝の一字をとって「輝元」とし、この年初陣を果たしている。
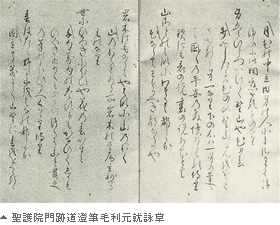 天正四(一五七六)年、織田信長に追放された足利義昭を保護し、上杉謙信や本願寺顕如と協力して、信長包囲網に加わった。当初は優勢だったが、謙信が亡くなり、毛利水軍が九鬼嘉隆の水軍に敗れ、家臣の宇喜多直家の離反、石山本願寺の降伏、秀吉の毛利攻めが始まるなど窮地に陥る。天正十(一五八二)年、明智光秀による本能寺の変が起こると、秀吉と和睦を結び、輝元は最悪の事態を脱した。 天正四(一五七六)年、織田信長に追放された足利義昭を保護し、上杉謙信や本願寺顕如と協力して、信長包囲網に加わった。当初は優勢だったが、謙信が亡くなり、毛利水軍が九鬼嘉隆の水軍に敗れ、家臣の宇喜多直家の離反、石山本願寺の降伏、秀吉の毛利攻めが始まるなど窮地に陥る。天正十(一五八二)年、明智光秀による本能寺の変が起こると、秀吉と和睦を結び、輝元は最悪の事態を脱した。

 信長の死後、豊臣秀吉と柴田勝家の覇権聖護院門跡道澄筆毛利元就詠草争いが勃発。輝元は両陣営から味方になるよう説得されるが中立を保つ。その後、勝家が倒されると輝元は秀吉の家臣となり、九州攻めや中国攻めの先鋒を務め、二度の朝鮮出兵にも従う。これまでの功績を評価され、五大老に任じられる。慶長三(一五九八)年、秀吉死去の際、臨終間近な秀吉に遺児秀頼の補佐を託されている。 信長の死後、豊臣秀吉と柴田勝家の覇権聖護院門跡道澄筆毛利元就詠草争いが勃発。輝元は両陣営から味方になるよう説得されるが中立を保つ。その後、勝家が倒されると輝元は秀吉の家臣となり、九州攻めや中国攻めの先鋒を務め、二度の朝鮮出兵にも従う。これまでの功績を評価され、五大老に任じられる。慶長三(一五九八)年、秀吉死去の際、臨終間近な秀吉に遺児秀頼の補佐を託されている。
德川家康と石田三成による対立が武力闘争に発展。天下分け目の決戦、関ヶ原の戦いとなる。輝元は三成らに推されて西軍の総大将に任じられ、大阪城西の丸に入ったが自身は関ケ原に出陣することなく不戦を貫く。合戦後、責任をとり出家。剃髪して幻庵宗瑞と称し、慶長八(一六〇三)年、江戸に出向き家康に謝罪、領地を周防・長門三十七万石に減ぜられるも毛利家は安堵される。寛永二(一六二五)年、萩城の四本松邸で死去。享年七十三歳であった。
輝元による慶長の復興
 三井寺は源氏・平家の対立や、山門派と寺門派の確執が原因で何度も焼き討ちや、闕所(けっしょ)に遭っている。 三井寺は源氏・平家の対立や、山門派と寺門派の確執が原因で何度も焼き討ちや、闕所(けっしょ)に遭っている。
豊臣秀吉による文禄四(一五九五)年の闕所は特に厳しいものであった。「闕所」とは家屋敷・家財さらに領有する所領を没収する処罰のことで、三井寺にある堂塔はまたたく間に、解体された。現在の延暦寺の釈迦堂はこの時解体された金堂を移築したものである。
秀吉が三井寺を闕所とした理由はよくわかっていないが、秀吉がこの闕所をもって三井寺の法脈を絶やそうとしたわけではなかった。

なぜなら、三井寺の信仰の根幹である本尊、弥勒菩薩をはじめ黄不動尊・智証大師坐像(御骨大師像・国宝)やその他の仏像宝物等を照高院に預けさせ、道澄のもとに遷された。また約六十名の僧侶も道澄に預けられていた。

道澄はひたすら三井寺の復興を念じ、秀吉に対して赦免を働きかける。慶長三(一五九八)年八月、毛利輝元、前田利家、徳川家康等の五大老連名による三井寺再興の許可を得、闕所の処分が解かれる。秀吉の死の前日であった。
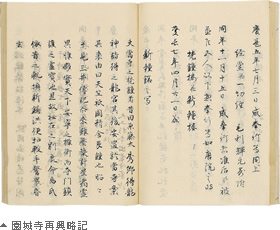 取り壊された堂塔のなかで最初に再建されたのが、開祖円珍をまつる唐院である。慶長四年、闕所の処分が解かれた一年後には早くも完成。次に三井寺の本堂である金堂の工事は、慶長四(一五九九)年四月に手斧初めがあり、翌五年七月に竣工している。わずか一年という短時間で完成をみ、国宝・勧学院客殿の設立も、輝元の手腕に負うところが多かった。
取り壊された堂塔のなかで最初に再建されたのが、開祖円珍をまつる唐院である。慶長四年、闕所の処分が解かれた一年後には早くも完成。次に三井寺の本堂である金堂の工事は、慶長四(一五九九)年四月に手斧初めがあり、翌五年七月に竣工している。わずか一年という短時間で完成をみ、国宝・勧学院客殿の設立も、輝元の手腕に負うところが多かった。
輝元は京・伏見に長期逗留し、利松孫左衛門を奉行に、職人・人足三百人を供出し、自ら指揮をとり礎石六十八基を据えるという難工事を敢行している。重機がほとんどない当時、どのような方法で成しえたのか、今となっては想像もつかない。
 慶長三年から始まった三井寺の復興も、六年には甲賀郡の常楽寺にあった仁王門が徳川家康の寄進で現在の場所に移築され、寺僧の住居である諸堂舎も急ピッチで再建される。 慶長三年から始まった三井寺の復興も、六年には甲賀郡の常楽寺にあった仁王門が徳川家康の寄進で現在の場所に移築され、寺僧の住居である諸堂舎も急ピッチで再建される。
天下分け目の戦い、関ヶ原の合戦がまさに火ぶたを切ろうとする刹那、西軍の総大将輝元は、朝廷と仏門に影響力のある道澄との関係を保ちつつ、東軍有利に進む戦況のなか家康に恭順の姿勢を示し、戦国の乱世を生き残ろうとした。
 知行百二十二万石の大大名から、三十七万石の小藩領主に大減封となっても、家名や家臣のために生き抜いた輝元・・・。 知行百二十二万石の大大名から、三十七万石の小藩領主に大減封となっても、家名や家臣のために生き抜いた輝元・・・。
毛利輝元が寄進した一切経は、四百年の時を超え、八角輪蔵の中で静かに眠っている。 |