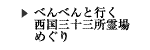|
八百屋お七の恋物語は、井原西鶴の浮世草子『好色五人女』をはじめ、
歌舞伎や浄瑠璃にもたびたび取り上げらた外題である。
その年の四月、大阪の豊竹座で人形浄瑠璃『潤色江戸紫』が上演されたと記録にある。
西鶴の描いた八百屋お七は、江戸本郷の八百屋八兵衛の一人娘で十六歳。
希に見る美女だった。天和二年(1682)も押し迫る師走二十八日、
折からのならい風(北東の季節風)に火はたちまち神田、下町へと燃えひろがり、
両国橋を越えて、本所、深川まで火の手が広がる。お七は母親に付き添われ、菩提寺の吉祥寺へ避難する。
同じ事情で寺に移ってきた人々と寝泊まりしながら当座の生活をおくる。
吉祥寺の寺小姓として働いていた吉三郎も十六歳。
お七はふとした事で、吉三郎の人差し指にささったトゲを抜くことになる。
これをきっかけに二人は手紙を交わす仲になるが、会う機会をつくれないまま、お寺での新年が明ける。
正月も十五日になり、急な葬式で寺中の僧侶が出払ったその機に、
今夜しかあの人に会う機会をないとお七は決心する。
寺の客間の寝床をそっと抜け出す。
お七の願いは成就するが、翌朝母親に見咎められ、避難先の吉祥寺から引き上げることになる。
親の厳しい監視下におかれるが、下女梅のはたらきで、こっそり文通だけは続いていた。
一方、吉三郎もお七会いたさに、里の子(農夫)に姿をやつし笠をかぶってキノコやツクシを八兵衛の店に売りに行く。
春の雪が降りしきる夕暮れ、八兵衛は哀れんでその子を土間に泊めてやる。
お七は、冷え込む土間で眠っている里の子に同情し、笠をそっとはずしてみると上品な顔立ちが現れ、吉三郎とわかる。
吉三郎の体は凍えきって、足も立たない。下女と二人がかりで部屋に運び込むが、隣は父親の部屋。
二人は灯の下に硯と紙を置き、もどかしい一夜の再会。筆談で永遠の愛を誓う。
しかし、お七にはそれきり、吉三郎に会う手立てが無かった。
ある風の強い夕暮れ、吉祥寺へ逃げたときの事を思い出し、「また、あんなことになれば、吉三郎さんに会える
種になるかもしれない」と、ふっと出来心から放火を思い立つ。少し、煙が上がったところで、取りおさえらる。
お七は素直に自白したが、火つけの重罪人として処刑された。
ほんのボヤで済んだ放火でも、火あぶりという重い刑で裁かれなければならないほど、当時の江戸は火災が多かった。
一方、吉三郎はお七に連絡できぬまま、吉祥寺境内にお七の卒塔婆を見て驚く。
あとを追うつもりで自殺をはかるが、僧侶たちや、お七の両親から説得され思いとどまる。
吉三郎は剃髪後、お七の菩提を弔い出家する……。西鶴の浮世絵草子『好色五人女』はここで終わる。
|